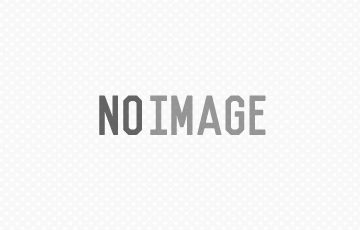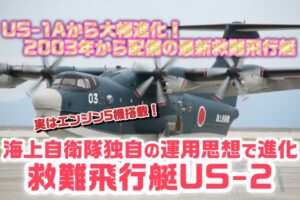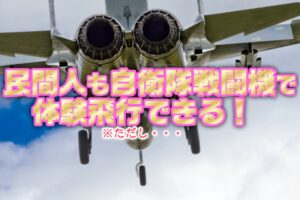自衛隊の射撃訓練は基本的に自衛隊の施設内や郊外の演習場、訓練場、基本射撃場で行う。
陸自には「体力検定」、「格闘検定」、そして「射撃検定」など、各隊員の基本的な技能を格付けする代表的な検定があるが、このうち射撃検定では隊員それぞれの射撃技術に応じて特級、準特級、1級、2級、3級まで各級位が付与される。
まれに確かに撃ったはずの弾丸が四次元空間に消えうせたのか、標的に弾痕が見当たらないことがある。心霊現象?いや、射手が的を外しただけで”弾痕不明”と言い、これはめでたく”級外”となる。おい。

89式小銃
基本射撃における実弾訓練では基本射場などで200mから300m先の紙的、金属や木製の的を89式小銃で狙う。
射撃場のうち、屋内射撃場は都内の一部駐屯地などに設置されている屋内型の拳銃・小銃射撃場で、近隣に配慮して全く発射音が外に漏れない。一方で陸自が配備しているM24対人狙撃銃は有効射程が1000メートルあるため、それに見合った距離での射撃訓練が行われる。警察の機動隊でも自衛隊の演習場で7.62mmおよび5.56mm口径の各装備品を用いて、射撃訓練を行うこともあるという。
海上自衛隊の艦艇乗員もやはり長い航海の間、船上で射撃訓練を行っており、空に揚げた風船を小銃や散弾銃(Benelli M3T)で撃つ訓練を行っている。
Contents
小銃分解結合
もちろん、射撃訓練の前には小銃を取り扱うための基本教育が前期教育課程の中で行われます。銃の通常の分解整備を普通分解と呼びますが、分解の手順を覚え、部品名称も頭と体で暗記する座学で、何回も小銃をバラして早く正確に組み立てていきます。
いろいろな射撃姿勢
もっとも基本的な姿勢に近い立ち撃ち、腹ばいになり両足を広げて体を安定させ、両肘を地面に立てて狙いを定め撃つ伏せ撃ち、さらに立てた片足の膝に肘を立てて小銃を構え撃つひざ撃ちの3つは、射撃姿勢が安定的で命中率が良く、自衛隊での小銃射撃における基本的な射撃要領だ。
こちらはけん銃射撃のスタイル。本来、けん銃は幹部自衛官や砲手などに貸与される装備品で片手撃ちによる射撃訓練が行われていました。
しかし、昨今では直面すべき対テロ戦争の現実性から、閉所戦闘など左右どちらの敵にも咄嗟に対応できるように、また、より安定した姿勢であることから両手撃ちスタイルに変更されています。
9mm拳銃の有効射程距離はたったの30メートル。しかも移動しながらの射撃では、なおさら当たらないものですが、陸自の特殊部隊「特殊作戦群」では歩きながら、あるいは走りながら標的をけん銃で撃つ訓練をしています。
ただ、2015年に公開されている警視庁・神奈川県警察特殊部隊SATの公開訓練動画ではSAT隊員が、MP5からP226Rけん銃へスイッチングする際に、両手射撃のほか、片手での射撃も披露していますから、この業界から片手撃ちが完全に廃れたわけではありません。
小銃に取り付けられる光学照準器とは?
自衛隊の小銃には、狙撃用のスコープ、それに近接戦闘用のダットサイトが搭載される場合もあります。

ダットサイトを装着した89式小銃を射撃する陸自隊員。(U.S. Marine Corps photo by Sgt. Brandon L. Saunders/released)
通常の照準用スコープが高倍率であるのに対して、ダットサイトは無倍率か低倍率になっています。見え方の違いは通常のスコープが、十字のクロスですが、ダットサイトは赤や緑色の光点(ドット)を電池駆動や放射性物質、あるいは太陽光でレンズの中央に投影させます。
このような仕組みで、ターゲットを素早く狙えるのがダットサイト、高倍率で遠くの目標を正確に狙うのがスコープと、それぞれ役割があります。
高倍率のスコープでサイティングした際の見え方。狙撃銃に搭載ならば、数百メートル先の目標を狙える。
ダットサイトのACOG(Advanced Combat Optical Gunsight)でサイティングした際の見え方。赤いドットがレンズ中央に浮かび上がっている。比較的近距離での交戦を考慮されて開発された光学照準器だ。
陸自では過去、 隊員が自費あるいは部隊単位で買ったタスコ(サイトロンジャパン)のMD-33型ダットサイトを小銃に載せ、研究を行ってきました。その結果、自衛隊の戦闘訓練においてもダットサイトが有効であることがわかり、現在では正式に官給品としてダットサイトの配備を行っています。
タスコに代わり、辰野や東芝電波プロダクツが製造を受注しており、正式名称を89式小銃用照準補助具と言います。
アメリカ軍では以前から広く配備されていますが、現在では陸自普通科連隊でもダットサイトはかなりポピュラーになっています。自衛隊のみならず、現在、警視庁などでも刑事部特殊捜査班がベレッタM92バーテックに、警備部のSATがMP5に搭載して運用しています。
自衛隊では小銃の側面にバケット状の袋を取り付けて薬きょうを回収
自衛隊では受領した弾丸と同じ数の空薬莢を返納しなければならないため、必ず撃ち終えたすべての弾丸の薬きょうを回収する手はずだ。
通常は薬きょうを回収するための袋状のカートキャッチャーが小銃側面に取り付けられているが、想定中に気がつかず外れるなどして、万が一にも薬きょうを紛失した場合は部隊全員での大捜索となる。
これは自衛隊の厳格な官給品管理を象徴する出来事として、時折ニュースになるほどだ。
熊本県で陸上自衛隊が薬きょうを紛失し、1000人を超える態勢で捜索する事態となりました。 紛失したのは89式5.56ミリ小銃弾射ち殻薬きょうです。 第42普通科連隊は、25日午前、熊本県内の駐屯地から演習場まで木箱に入れて運んでいた薬きょうが、車両の荷台で散乱しているのに気づき、輸送した1万発のうち7発足りないことがわかりました。 その後、25日午後10時までに、3発を演習場の敷地内で、3発を一般道で発見し回収しました。 そして、26日午前6時から最終的に1300人態勢を組み探したところ、最後の1発を一般道で発見、延べ14時間で7発全てを回収しました。
引用元 TBS
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2526338.html
薬きょうをなくして大捜索があったことを日米合同演習の米兵と自衛隊との飲み会で言っても、信じてもらえないこともあるという。
自衛隊員の射撃技術は低いの?高いの?
では、自衛隊員の射撃技能は世界の軍隊の兵士と比べてみた場合、高いのだろうか。「国際射撃大会でブービー賞だった自衛隊精鋭部隊」という記事が2012年の週刊文春に掲載されたが、これは武器の選択を誤ったのが原因とされている。
この大会への派遣では中央即応集団(現在の陸上総隊)の精鋭が選ばれたが、本来なら平成14年に採用されたM24SWS対人狙撃銃で臨むべき長射程の種目をダットサイトつきの89式で挑んだという。自衛隊が持っていった銃は拳銃と89式小銃とMINIMIだけ。なぜM24を持っていかなかったのかは定かではないが、せめてスコープつきの64式でもあれば少しは結果が違ったかもしれない。
なお、これは2012年の結果だが、2013年度の結果はなんと陸自が世界の軍隊と競合の中、9位になっている。
実弾を使わない仮想シミュレーターを使った射撃訓練や市街地戦闘訓練とは?

自衛隊は安全な仮想射撃訓練を重視している
ほかにも、陸自ではビデオシミュレーターを使った仮想射撃訓練も行っています。
自衛隊では安全に銃の訓練を行うために、実弾を使わない、イミテーション銃によるビデオシミュレーター訓練や、エアガンによる屋内や閉所でのCQB(近接戦闘)訓練、ペイントボールガンなどでもより実践的な訓練を行っています。
昨今では、弾丸の命中位置をセンサーで即座に判定する小火器射撃評価システムという装備が陸自に導入されています。
射手の手元に画面を備えた映像装置があり、そこに射撃の結果が映し出され、射手が射撃のみに集中できる利点があります。
89式の仮想射撃シミュレーターの実際の様子です。ビデオ映像に向かって銃を撃ちます。
銃はガスを利用し、89式小銃本来のリコイル・フィーリングとファイアリングサウンドも忠実に再現。
映像は多彩なシーンを映し出すことが可能で、将来起きうるであろう日本国内での大規模なテロ、市街戦を想定した対テロ戦闘訓練も可能。マンガさながらのオフィス街での銃撃戦はまさにアジアで一人負け、斜陽没落・格差貧困・1億総底辺派遣となった未来の日本の街角でしょうか。”三丁目の戦火”って感じです。震えが止まらない。
敵に命中すると人体はブバッ!とはじけ飛び、車両は爆発し、PUBGも顔負け。
このように自衛隊では、安全で屋内でも行える実弾を使わない仮想訓練を導入しているわけです。
自衛隊はエアガンで訓練している!使っているガンはどこ製品?ジュールは規制値内?
なんと自衛隊は訓練で89式のエアガンを使っているらしい?(画像は実弾で撃ち合った奇跡の実銃89式)
自衛隊がエアガンで訓練しているというのは本当なのだろうか。実は本当なのだ。自衛隊の市街地戦闘訓練における近接戦闘訓練を支える安全資機材はなんとエアガンだったのである!君よ知るや、マルイの89!
実は、自衛隊では稀に実弾で撃ち合うこともありますが、2006年からはエアガンを用いた「近接戦闘訓練」いわゆるCQBトレーニングを正式な訓練として行っています。
なぜ、自衛隊はエアガンを用いた訓練を取り入れたのでしょうか。
なぜ自衛隊がエアガンで訓練することになったのか
そもそも、自衛隊では実弾を使わない実戦的な戦闘訓練として、以前から実銃に装着する「バトラー」と呼ばれるレーザー式射撃訓練装置を使って「よりリアルな」訓練を行っていました。
バトラーは実弾の代わりにレーザー光線を用いて命中判定をする交戦用訓練装置で、発光部を小銃、機関銃に装着し、受光部(ヒット・インジケーター)をハーネスで各隊員の身体に着装する装具です。
陸上自衛隊部隊訓練評価隊……専用の迷彩服まで配備した陸自のアグレッサー(仮想敵)部隊
現在、陸上自衛隊北富士駐屯地には普通科部隊の戦闘訓練で対抗部隊として活動する専門部隊、その名も「部隊訓練評価隊」が編制されています。
いわゆるアグレッサー部隊であり、バトラーを使って各地の普通科部隊に実戦的な訓練を施しています。
このバトラーは、隊員個人が身に着ける装具と小銃などに取り付けるパーツから構成されたレーザー光線による交戦訓練システムです。実弾を使用せず、安全に訓練ができるのが特徴です。
銃に取り付けられたレーザー発射装置から投影されたレーザー光が、隊員の身体の各部に取り付けられた受光部に受光すると、ブザーが鳴り被弾を知らせます。現在は新たにアップグレードしたタイプが配備されており、被弾すると液晶モニターに被弾によるダメージの状態が表示されます。従来型に比べ、より細かな当たり判定が行われており、ゾンビ行為ができなくなりました。
専用の迷彩服と特別な塗装を施した専用車両
評価隊には平成21年度から、専用の迷彩服となる「対抗部隊用迷彩服」が配備されています。
これは陸上自衛隊でかつて配備されていた迷彩服1型のパターンとほぼ同じですが、やや、黄色みが強くなっており独特の色合いをしています。
また、評価隊には戦闘車両も配置されており、一般部隊では2色塗装にされている車両が評価隊では3色と、こちらも特別なカラーになっています。
また、対戦車火器や戦車にも装着が可能で、効果的な戦闘訓練が行えます。このシステムが描写された映画にアメリカ海兵隊教育隊の訓練と実戦を描いた「ハートブレイクリッジ Heartbreak Ridge」があります。
とはいっても、受光部が装着された部分しか命中判定ができず、おおまかな判定しかできませんでした。
さらに、昨今問題となっているゲリコマからの対処訓練として、陸自では市街地戦闘訓練が必要になってきました。
とくに建物内などでの近接戦闘にも対処する必要性があることから、全国の部隊では演習場内に専用の訓練施設を建設し、ビルや民家、スーパーなどといった実際の家屋を模した建物がつくられ、閉所における戦闘を学んでいるところです。
そして、そのために用いられるのが「閉所戦闘訓練用教材」こと89式タイプのエアガンです。
この東京マルイ製の電動ガン、実は以前から非公式な近接戦闘訓練メニューとして、一部の戦闘職種の部隊ではTMの電動ガンを使用して近接&閉所戦闘訓練(いわゆる建物内などでのCQB訓練)を行っていました。
2006年にTMから89式小銃のエアソフトガンが発売されましたが、実はこの製品の開発には自衛隊が公式協力しており図面が提供されました。
このため、過去に例のないほどリアルなエアガンが誕生しました。
自衛隊で使用されているものは自衛隊特別仕様の89式自動小銃型エアソフトガンです。市販品とどこが違うのかというと、ストックの色がOD、専用ガンケースに入れて納入されている……など。
部隊によっては銃身を各種カラーで塗色しています。
ミリブロNews様では、平成21年度 日米共同訓練~市街地戦闘(MOUT)編~にて米軍との合同訓練時に公開された銃身を紫色にした89式訓練銃の写真を掲載されています。
http://news.militaryblog.jp/e89821.html
ちなみに、このマルイ製89式エアガンは海外のドラマや映画にも登場しています。なぜか、台湾のテレビドラマBlack & White痞子英雄では反社会勢力側が使う銃として登場していました。
さらには、あの超大作「コマンドー」のロシア版リメイク作品「コマンドーR」にもマルイ製が登場しています。主人公の敵が日本の自衛隊なので……。
自衛隊の89式電動ガン……実は東京マルイよりも早く作っていた会社があった
東京マルイが防衛省の公式な協力を得て89式電動ガンを製造販売したのが2006年。しかし、実は東京マルイより前に89式電動ガンの開発を行っていた会社があります。それが「89R」を出したキャロット社。
もともと「89R」は既存のマルイ製電動ガンのパーツを利用した外装キットでしたが、その後キャロットでは完成済み89式電動ガンも販売していました(その直後に東京マルイが89式電動ガンをを開発)。
キャロットでは「89R」を開発するにあたり、自衛隊や豊和工業から公式に図面提供などは一切受けていないそうです。協力を要請したかは定かではありませんが、おそらく時代が時代だけに受けたくても受けられなかったのでしょう。
当時の自衛隊は萌えキャラで悪乗りするような「開かれた組織」ではなく、そっち方面のゲートは閉じていたため、市販の資料や写真、開発スタッフが駐屯地祭へ足を運んでの取材が開発ベースとなっています。
また、当時は市民団体が自衛隊が市民に銃を触らせたとして自衛隊を告発することもなく、自衛隊の銃器展示も比較的緩やかな実情もありました。
皮肉なことにキャロット製89式キットのクオリティの高さ、すなわち再現性は「正式に自衛隊が開発協力した東京マルイの89式」の発売によって、証明されてしまったこともゲーマーには興味深いそうです。
もちろん、自衛隊側から正式に図面を提供された東京マルイ製89式も、そのすべてが正確に作られているわけではありません。グリップにはモーターが入るため実物より若干太く、またバッテリーへの雨水対策として、ハンドガードは実銃と別仕様。
また、エアソフトガン・ユーザーへの安全を確保するため、限られた素材で強度を出すように肉厚の部分もあります。
さらには、あえて実物と細部を異なる仕様にし、実銃のパーツを取り付けられないようにするという「実銃ユーザー」に対する安全面の配慮もされたうえでの開発です。
残念ながらキャロット製89式電動ガンは東京マルイの製品ほどの成功はしませんでしたが、現在キャロットでは陸上自衛隊にラバー製イミテーション89式を納入しており、この製品はとくに西部方面普通科連隊の水路潜入訓練で使用されるなど活躍しているようです。
自衛隊の訓練用89式……ペイント弾も
さて「よりリアルな環境で戦闘訓練するのが狙い」との理由から、防衛省が制式に配備した89式エアガンでは着弾後、血のりのように赤くべっとり染まるペイント弾の使用も想定されています。
また、このほかにも自衛隊が採用している模擬銃にはペイントボール専用発射銃があります。海上自衛隊特殊部隊「特別警備隊」ではMP5を採用しているため、株式会社PDI製品のMP5型シミュレーター(ペイントボール発射タイプ)が海上自衛隊第一術科学校へ納入されています。また、PDIでも89式型訓練銃の開発研究がされています。
マルイの89式との違いは、6ミリBB弾ではなく11ミリのラバーボール弾やペイント弾が発射できる点および、駆動方式がガス圧です。
http://ascii.jp/elem/000/000/076/76461/index-2.html
さらにPDI社では、AK47やM4A1など、世界中の軍隊や警察が使用する小銃を訓練用資機材としてリアルに再現したPDIシミュレーターズという製品もラインナップしています。
これらは完全に銃刀法に適合しており、何ら問題なく規制の範囲内で使用できます。使用する弾丸は11ミリのペイントボール弾。アルミケースのカートに装てんされ、排出されます。このためアルミケースがコンクリ―トに落下すれば実銃同様の薬きょう落下音を奏でられ、益々リアルな訓練環境を演出できるとのこと。
ペイント弾といえば、新谷かおるさんの女性傭兵を主人公とした傑作作品「砂の薔薇」でもおなじみで、閉所や家屋内などで実戦的な訓練をするための安全な模擬弾です。着弾すると弾丸の中の水性塗料が飛び散るため命中判定が容易にできます。赤い塗料であれば血ノリのように。ペイント弾は警察や軍隊の訓練のほかスポーツのペイントボールゲイムなどでも使用されています。
2017年11月になると東京マルイでは2018年の新製品として同社が既に発売している89式電動ガンに続いて、ガスブローバックタイプの89式も発売すると発表しました。
すでに自衛隊に訓練用品を納入している一部の専門商社ではこの東京マルイ製の新商品89式ガスブローバックをカタログに掲載し、自衛隊へ売り込みをはかっています。
もともと、エアソフトガンによる訓練は米軍が始めた
沖縄駐留アメリカ海兵隊では80年代、アサヒファイアーアームズという会社のFNC型エアガンを納入して訓練していたと80年代末のエアソフトガンのカタログに記載されていました。
また、グアムの警察ではユースエンジニアリング社のガスブローバック式MP5を使用して訓練を行っていたという事実もあります。自衛隊としてもエアガンでの訓練が実戦で役に立つと判断したから採用したわけです。
基本的にBB弾でも極端な近距離でのトレーニングでは、6ミリのプラスチック製BB弾と言えど、当たると痛いわけですから、自分の体に弾が当たらないようにするため、本能的に「弾が当たらない防衛技術」を、より恐怖心をもって学習できるわけです。
このように訓練の臨場感をさらにを強化するために、エアガンでも緊張感をもって訓練に臨めます。とくにエアガン訓練は日本では最も安全でクリーンな”射撃訓練”でしょう。
エアガンでは限界も……
ただし、エアガンの訓練でもやはり限界があります。何より、エアガンと実銃では銃の操作手順も発射の反動も音も別物です。そこで、各国ではSimunition – Non-Lethal Training Ammunitionを導入する事例も増えています。
シミュニッションは「ノン・リーサル・トレーニング・アムニッション」の名のとおり、安全な訓練用資機材であり、各国の軍隊や法執行機関が導入しています。これは、実銃そのもので安全に訓練ができるシステムです。
在沖縄アメリカ海兵隊の訓練では、実銃とペイント弾による野外での実戦的な訓練が行われています。
これは実銃のM16アサルトライフルの機関部を模擬のペイント弾が発射できる専用部品に換装するシステムですが、弾丸の初速は日本のエアソフトガンよりも早く危険なため、兵士は眼だけでなく顔全体を守るためのSCOTT(スコット)のフルフェイスゴーグルマスクを着用します。
まとめ
- 自衛隊は射撃訓練を多様な課程で行う。
- ビデオシミュレーターを使った仮想的な訓練も行う
- 自衛隊は東京マルイ製で市販品とほぼ同じ89式電動エアガンで閉所戦闘訓練をしている。
- マルイのエアガン以外にもペイントガンを訓練に導入している。
なるほど、実銃ではないイミテーションの89式も自衛隊にとっては立派な”訓練資材”ってわけだね!オモチャを学習に取り入れる動きは公立学校でのニンテンドーのゲーム機導入が目新しいけど、実は自衛隊や米軍のほうが一歩先なんだね。
というわけで、エアガンやビデオシミュレーター訓練は現代の自衛隊では普通です。





![ストライクアンドタクティカルマガジン 2015年 07 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61hWahIhFBL._SL500_.jpg)