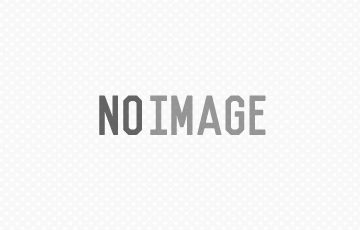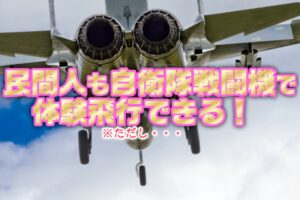現行配備の「88式鉄帽」はどのくらいつおい?

スポンサード リンク
実はこの「鉄帽」、鉄製ではない!
88式鉄帽は鉄製ではなく、とっても軽いケブラーと呼ばれる素材でできています。自衛隊では66式の頃からヘルメットを「てっぱち(鉄鉢)」と俗称で呼んでいますが、これは旧日本軍から呼称される伝統的な用語なのです。ケブラーは防弾チョッキでポピュラーな素材ですが、88式鉄帽の防弾性能は飛び散る榴散弾や砲弾の破片や、9ミリ拳銃弾から頭を保護するくらいの防護力が想定されています。このため、専ら榴弾の破片などを防ぐことが目的のようです。なお、海上保安庁や警察にも一般警察官用として88式ヘルメットをグレー色にしたものを配備しています。なお、海上自衛隊特殊部隊や西部方面普通科連隊などでは水路潜入訓練の際に88式ヘルメットを使用せず、軽量なスポーツ用の「プロテック」ヘルメットを使用しています。
13年から配備の88式鉄帽2型とは?
2013年からは新改良された88式鉄帽2型が配備されるようになりました。防弾性能は旧型同様ですが、軽量化されており、4点式顎ひもも標準装備となっています。
旧型の66式鉄帽
過去に陸自で広く配備されていたのが、米軍のM1ヘルメットを参考に日本国内で生産した「66式鉄帽」です。ところが、なかなか日本人の頭部とは合わないために、隊員からはあまり評判がよくありませんでした。おまけにヒサシの部分が長く、64式小銃の可倒式リアサイトと干渉してしまい、注意しないとリアサイトが前にパタパタ倒れちゃうのです。また、現在の88式に比べると材質も合金製でとても重いため、隊員に負担がかかっていたそうです。なお、現用の88式は66式に比べ300グラムも軽くなっているんです。一方で、この66式は完全に退役したわけではなく、後方部隊や予備自衛官補の訓練で貸与されることがあるほか、なんと防衛大臣や幕僚にも貸与されており現役なんです。自衛隊においては旧式装備は後方職種、詮ずるところ戦闘を主任務としない部隊に回されるのが常になっていますが、テッパチについても例外ではなく、まだまだ現役です。
鉄帽覆い
通常、66式、88式鉄帽には本体自体にあらかじめ陸自はOD、航空自衛隊は暗いグレー、海上自衛隊は明るいグレーの各色がそれぞれ下地として塗装されています。3自衛隊では迷彩のカバー「鉄帽覆い」をかぶせて使用します。

J.M.E. 陸自新迷彩 130 偽装網新迷彩ひらひら付 鉄帽用(ヘルメット用)
しかし、海自の艦艇で使用する場合は鉄帽覆いを用いません。第一空挺団はパレード時に自隊を強調するためか、ノンカバーの88式に第一空挺団のシンボルマークを描いた特別仕様の88式を被っています。
4883929647 | 自衛隊の謎検証委員会 | 彩図社 | ¥ 670 | 2013-12-24
ライナー(中帽)
一方、自衛隊には中帽、ライナーと呼ばれる樹脂製ヘルメットも配備されています。これは工事のドカヘルと同等の強度を持ったもので災害派遣や体験入隊で被るのも専らこれです。東日本大震災で救助や復興任務にあたった隊員たちはこのライナーに東北復興への思いを込めたメッセージ・シールを貼って活動しました。
自衛隊の「テッパチとウソッパチ」
一方で「ウソッパチ」なんてものがあります。旧型の66式鉄帽を模したプラスチック製のレプリカヘルメットなのですが、本物の鉄製ヘルメットに比べ軽いのでカバーをかけて”偽装”したうえでコッソリと愛用している隊員が多かったようです。形状は細部で異なるものの、カバーをかければまずバレず愛用者も多かったのですが、安全性に問題があり公式には使用は禁止されていました。
Photo by Gunnery Sgt. Ricardo Morales(PD)